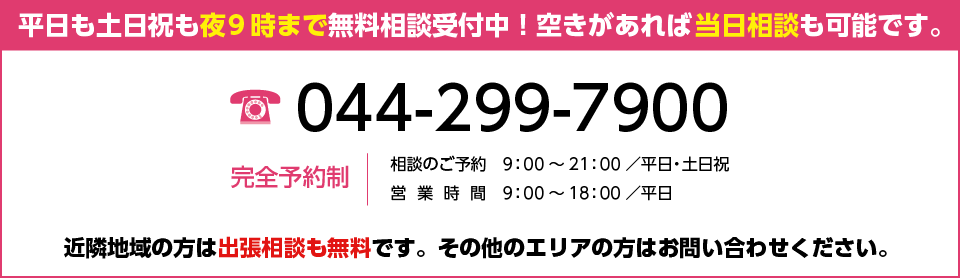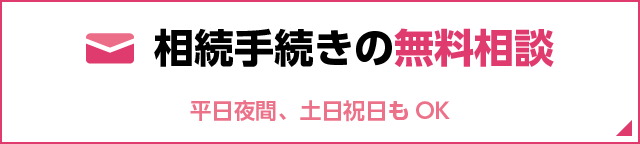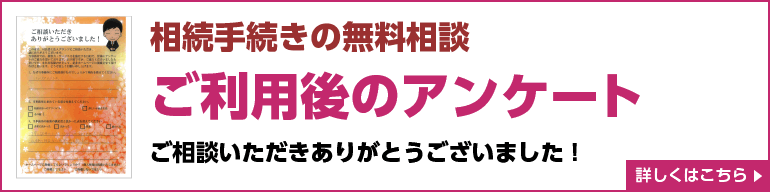2025年相続登記の新ルールとは?所有者情報の「事前登録」で安心相続
2025年4月21日から変更されている不動産登記・相続登記でもメールアドレスの記載が必要に
2025年4月21日から、不動産の登記申請書に新たに「ふりがな」「生年月日」「メールアドレス」の3つの情報を記載することが義務化されています。
これまで必要だった「氏名」「住所」に加えて、これらを合わせて「検索用情報」と呼びます。
この変更は、相続登記(亡くなった方から不動産を相続する名義変更登記)を申請する際にも対象となります。
つまり、相続登記の際にも、原則として新しく所有者となる方のメールアドレスを申請書に記載する必要があるのです。
なぜメールアドレスが必要なのか?背景は「所有者不明土地問題」
背景にあるのは、以前から全国で問題となっている「所有者不明土地」の増加です。
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わっても、登記の変更が行われないまま放置されるケースが多く、公共事業などの際に障害になることが増えていました。
そこで国は、2026年4月から、所有者に変更があった場合、登記官が自動で変更をしてくれる制度を導入する予定です。これがいわゆる「スマート変更登記」です。
スマート変更登記とは?
- 所有者が自ら登記変更しなくても、
- 法務局が住民基本台帳(住基ネット)と連携し、
- 自動で住所や氏名の変更登記をしてくれる仕組みです。
でも、自動変更するには「本人の同意」が必要です
登記簿の情報は誰でも閲覧できるため、たとえばDV被害者やストーカー被害者などが、加害者に住所を知られてしまうリスクもあります。
そのため、勝手に登記を変更するのではなく、所有者本人に「登記変更していいか」の承諾を取る必要があるのです。
この承諾のための連絡手段として、メールアドレスの登録が必要になったというわけです。
メールアドレスが必要となる登記の種類
以下の登記申請の際には、検索用情報(ふりがな・生年月日・メールアドレス)の記載が必要です。
- 所有権の保存登記(新築時など)
- 所有権の移転登記(相続・売買など)
- 所有権の更正登記(名前の誤記などの訂正)
- 合体による登記など
特に一般の方が関わることが多いのは「相続登記」「売買登記」となります。
よくある質問と実務上の注意点
Q1. メールアドレスがない人はどうすれば?
→「メールアドレスなし」と申請書に記載すればOKです。
その場合は、法務局からは書面による確認通知が自宅に送られます。
Q2. 親族のメールアドレスを使ってもよい?
→原則として「本人が使っているメールアドレス」を求められています。
ただし、実務上は確認手段がないため、親族のアドレスでも受理はされるかもしれません。
※それでも、後々のトラブルを避けるために本人のメールアドレスを使用しましょう。
Q3. メールアドレスを後から変更したいときは?
→申請時に送られてくるメールには「認証キー(10桁)」が記載されており、この認証キーを使えば、Web上でメールアドレスの変更手続きが可能です。
既に不動産を持っている人も、申出が可能です
この新制度は、登記の申請を伴わなくても、単独で「検索用情報」の申出をすることができます。
すでに不動産をお持ちの方も、以下の方法で申出が可能です。
- 法務局への書面申出(郵送または持参)
- オンラインでの申請(かんたん登記申請)
- 司法書士に代行依頼
不動産業者・相続担当者・司法書士との連携も重要に
売買・相続登記の現場では、司法書士が申請を代行することが多いです。
その際に「メールアドレスをどうするか?」という説明や確認作業が必須となるため、司法書士としては取引の準備段階での情報確認が重要となっています。
まとめ 相続登記前にメールアドレスを確認しておこう
2025年4月21日以降の登記制度変更により、メールアドレスや生年月日の事前準備が必須となりました。
これは、将来的に利用者の負担を軽くするための重要な仕組みです。
ただし、認証キーを紛失してしまうと、後々の手続きに支障が出る可能性があるというご指摘もあります。
そのため、メールアドレスの登録をご希望されない場合は、登記申請書の「その他事項欄」(オンライン申請の場合)に「登記名義人につきメールアドレスなし」旨を記載するか、登記を依頼されている司法書士へその旨をお伝えいただく対応が必要となります。
令和7年7月31日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
相続のことなら司法書士法人グランツの無料相談へ。川崎・横浜他